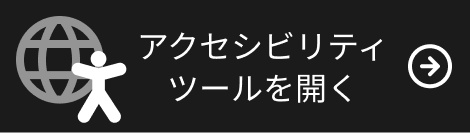- HOME
- 小児科
かぜ
概要ウイルスや細菌の感染に対して体が反応し、発熱や気道症状(鼻水・鼻づまり・咳・のどの痛みなど)が起きる病状です。
発熱は通常、免疫力を高めて病原体と戦うために脳の指令によって体温の設定値が上げられた結果です。
かぜの原因のほとんどがウイルスですが、その種類がとても多く、かぜには何度も罹ります。
感染症なので必ずどこかで誰かからうつる病気ですが、寒かったり疲れたりして免疫力が低下したときに発症しやすくなります。
とくに保育園などへの通園を始めたばかりの頃には、繰り返しいろんなかぜのウイルスに感染し、毎月のようにかぜを引くこともあります。そのようにして、だんだんと免疫を付けていくのです。
かぜに中耳炎や副鼻腔炎や気管支炎や胃腸炎や、ときにはもっと重症の合併症を併発することもあります。
高熱が続いたり咳がひどくなったときは、早めに医療機関を受診してください。
原因がマイコプラズマなどの細菌感染の場合は、抗生剤を処方することもありますが、通常は、かぜに効く抗生剤はありません。
鼻水、咳、痰など、お困りの症状をそれぞれやわらげるために対症療法を行います。
熱が高くても比較的元気なら必ずしも解熱する必要はありませんが、高熱で食事も摂れないような時には解熱剤を使ってください。
中耳炎や副鼻腔炎や気管支炎を併発した場合は、それに応じた薬を追加する場合もあります。
インフルエンザ
概要インフルエンザウイルスの感染による、かぜに似た、かぜよりも激烈に発症する感染症です。
ウイルスが体内で増えるスピードが速いので、体も急いで反応し、急に高熱が出ます。そのため、寒気・ふるえ・節々の痛み・倦怠感を伴います。
咳などの症状はむしろ遅れて出始めますが、最近(2024-2025年)流行しているA型インフルエンザは、最初から咳やのどの痛みを伴うことも多いようです。
流行する型は1シーズンに1つとは限らないので、1シーズンに2回罹ることもあります。
インフルエンザは抗原検査によって診断できます。鼻咽腔を綿棒でぬぐい、10分以内に結果が判明します。
状況と病状によっては、検査を行わなくてもインフルエンザと診断する場合もあります。
ときどき、家庭内でインフルエンザとコロナが同時に発生することもあるので、両方の疑いがある場合は、両方同時検査する必要があります。
希望があれば抗インフルエンザ薬を処方します。内服薬と吸入薬(口から吸う薬)があります。
当院では原則として、内服薬はタミフル(またはオセルタミビル)、吸入薬はイナビルを処方します。
タミフルは、1日2回、5日間服用する薬です。38キロ未満のお子さんは粉薬になります。0歳でも服用できます。
イナビルは、ストローのような吸い口をくわえて粉薬を口から吸い込む薬です。上手に吸えるのは、おおむね6歳以上ですが、個人差があります。1日(1回)だけで終了します。
抗インフルエンザ薬は、インフルエンザウイルスを早く減らして早く熱を下げる効果が期待できます。その意味では、すでに熱が峠を越えた方への処方の必要性は乏しいと考えられます。
手足口病
概要病名の通り、手と足と口に発疹ができる、ウイルス感染症です。
手のひらや足の裏には水疱ができやすく、手の指や手の甲や肘や膝付近には丘疹(飛び出た発疹)ができることが多いようですが、発疹の出る場所や個数はさまざま。お尻にもできやすいのが特徴です。
口の中では、舌やノドの手前側の天井(硬口蓋)に赤い発疹ができるので、ヘルパンギーナの発疹とは場所が少し異なります。
初日だけ発熱する事が多く、最初はヘルパンギーナとの区別が付かないこともありますが、2日以上高熱が続くことはあまりありません。手足の発疹が口よりも遅れて出てくることや、その反対に口の発疹の方が遅れることもあります。
保育園などで夏によく流行しますが、それ以外の季節でも発生します。家庭内で、きょうだいや親に感染することもあります。
ウイルスは何種類もあるので、何度も罹ります。1年に2回以上罹る場合もあります。
かぜと同様、特効薬はありません。かぜの様な症状があれば、その薬を処方する場合もあります。皮膚病ではないので、発疹に塗る薬もありませんが、たまたま発疹を掻いてしまうと痒み始めることがあり、その場合は消炎外用薬を使います。
コラムヘルパンギーナ
概要高熱とのどの発疹が特徴のウイルス感染症です。高熱が3,4日続き、のどの発疹が痛むために食事が摂りにくくなります。
すぐに下熱して手足に発疹が出始めた場合は、それはヘルパンギーナではなく手足口病です。そのように、初期には両者の区別が付きにくい場合もあります。
手足口病と同様にウイルスが何種類もあるので、何度も罹ることがあります。
のどの痛みが強いので、食事の内容を工夫して、とくに小さなお子さんでは脱水にならないように注意します。痛みを鎮めて食事を摂りやすくするために、適度なタイミングで解熱鎮痛剤を使うこともあります。
コラム溶連菌感染症
概要「A群β溶血性連鎖球菌(略して溶連菌)」という細菌に感染し、高熱と強いノドの痛みが起きる病気です。
のどが燃えるように赤くなり、よく見ると小さな赤いプツプツが密集していたりします。時には扁桃炎を起こすこともあります。また舌がプツプツと赤くなる「イチゴ舌」も特徴です。
下腹部や大腿部、ときには腕や顔などに小さな赤いブツブツが密集したような、あるいはザラッとした発疹が出ることもあり、しばしば痒みを伴います。
友達や家族に感染者がいる事が多く、また治療をしても保菌状態になるお子さんもいて、再発しやすい疾患です。
この病気は昔から、心臓病(リウマチ熱)や腎臓病(溶連菌感染後急性糸球体腎炎)などの原因として知られています。
熱や咽頭痛が改善したあとぐらいのタイミングで、手や足のゆびの皮がむけることがあります。自然に治りますが、保湿剤などを使っても良いでしょう。
周囲での流行や典型的な咽頭・皮膚所見があれば容易に診断はつきますが、治療や合併症を考慮して、当院ではなるべく迅速検査をして診断を確定させています。咽頭を綿棒でぬぐい、10分程度で結果が判明します。
一般的なウイルス感染によるかぜとは異なり、細菌感染なので抗生剤(抗菌剤)が効きます。
通常は、病状の経過を見ながら5~10日間ほど抗生剤を服用します。当院では第一選択としてペニシリン系抗生剤(ワイドシリンなど)を処方しますが、再発例などではセフェム系抗生剤(フロモックスなど)を用いる場合もあります。
抗生剤の服用開始の24時間後までは感染力があると考えられるので、登園・登校は治療開始の2日後からにしましょう。
薬が効いてすぐに下熱して咽頭痛も消える場合が多いですが、合併症(続発症)を防ぐためにも、通常は抗生剤は処方通り飲みきってください。治りが悪い場合は別の感染症の併発の疑いもありますので、早めに医療機関にご相談ください。
続発症のうち急性糸球体腎炎を発見するために、抗生剤の服用終了後とその2,3週間後ごろに尿検査をします。むくみや血尿が出るようなら、その時点で検査が必要なので医療機関にご相談ください。
・溶連菌感染治療はシッカリと
・溶連菌感染が増えてますが、状況は複雑です
・溶連菌には抗生剤十分に
・それ、弁膜症かも
・溶連菌感染の初期症状
アデノウイルス感染症
概要アデノウイルスの感染による、かぜの一種です。ウイルスの種類が多く、高熱や咳、咽頭炎、結膜炎、下痢を起こすなど症状も様々です。
咽頭炎(のどの奥がイクラのように赤く腫れる)と結膜炎(朝は目が開かないほど目やにが出る)と高熱が揃えば、「咽頭結膜熱(通称プール熱)」という病状です。強い扁桃炎を起こすこともあります。
とくに結膜炎がひどく、目が赤く腫れて痛む場合は、「流行性角結膜炎(はやり目)」です。感染力が強いので家庭内で広がることがあります。
いわゆる「感染性胃腸炎」を引き起こす代表的なウイルスでもあり、高熱、嘔吐、下痢の順で発症することが多く、下痢はやや長引きます。
アデノウイルス感染後に、真っ赤な血尿が現れることがあります。「出血性膀胱炎」です。
咽頭炎や扁桃炎が強い場合や目やにが多いときは、咽頭や目やにをぬぐってウイルス検出検査をする場合があります。
また、おむつの持参便を使ってウイルス検査(迅速検査)を行う事もあります。いずれも院内検査で、15分程度で結果が判明します。
ただし、これらの検査の結果アデノウイルスが陽性でも陰性でも、治療方針は変わりません。
アデノウイルスはアルコール消毒が効きにくいため、とくに胃腸炎の乳児の世話をした後は、しっかり石鹸で手洗いをしなければなりません。
対症療法です。症状に応じて、解熱剤、かぜ薬、目薬、整腸剤などを処方します。
胃腸炎の場合は、経口補水液やゼリーなどを利用して、少しずつ摂取すると良いです。脱水の危険がある病状の場合は、点滴が必要です。
感染性胃腸炎
概要ウイルスや細菌の感染によって、嘔吐や下痢を起こす病気です。しばしば発熱します。
急な発熱に伴って1回だけ嘔吐したような場合は、インフルエンザなど別の感染症の場合があります。
保育園等で流行しやすい胃腸炎は、ロタ、アデノ、ノロなどのウイルス感染のことが多く、持参便でウイルス検査を行うことができます。
ただし、ノロウイルスの検査は、3歳~64歳の方は保険適応外となり、混合診療が禁じられているため診療費用全体が自費扱いになります。
ロタの便は乳白色~うぐいす色、アデノはもう少し黄緑色に近いことが多いようです。
これらのウイルスはアルコール消毒が効きにくいので注意が必要です。患者さんの世話をしたご家族は、水道水と石鹸で手を洗う必要があります。
細菌性の胃腸炎は、多くは食物から感染する食中毒です。潜伏期間が1週間以上のものもあり、原因の特定が難しい場合もあります。
カンピロバクター感染の場合、発症からしばらくして手足などの神経麻痺を起こす「ギランバレー症候群」を発症することがあり、注意が必要です。
ウイルス性の場合には特効薬はなく、飲食物の工夫をしてお腹を安静にします。脱水の危険があれば点滴が必要です。
細菌性胃腸炎には抗生剤を使います。原因菌が検出できなくても、状況から推定して治療を行う事もあります。
生の鶏肉(鶏刺しや鶏たたき)を食べて1~数日後に発症すれば、カンピロバクター感染と考えて、効果のある抗生剤を使います。
・「アルコール消毒」だけでは感染性胃腸炎は防げません
・インフルの次は胃腸炎?
・あえ物で食中毒
・ノロの検査をどうする
・餅つきでノロ感染
・新型ノロ流行か
・感染性胃腸炎